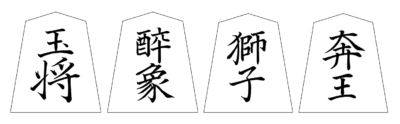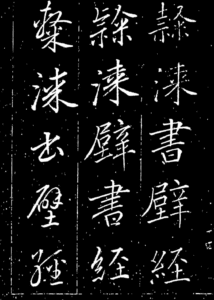|
2021/04/30サビの埋め込みをしました
|
|---|
|
彫埋駒と盛上げ駒の制作で、サビの埋め込みを行いました。サビの調合に少々手間取りましたが1回目の埋め込みが無事に終わりました。

ここから3回~4回かけて埋め込んでいきます。
サビは私の場合、1回分1組分だけ作るのは意外と難しいので、全回分を見込んで多めに作ってしまいます。残った分はラップにくるんで、空気をよく抜いて保管します。次回使用するときには、使う分を取り出して生漆を一滴加えてやるとキレが戻ります。

|
|
2021/03/27中将棋駒を作ってみたい
|
|---|
|
このところ息子を寝かしつけた後、夜な夜な字母紙の研究をしています。最近は中将棋に興味が出てきて資料を集めています。
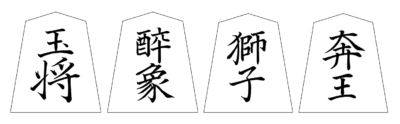
まだ全然これからですが、1から作るのは面白いです。
駒の種類も今まで知りませんでしたが、獅子と奔王はなかなかチートですね。獅子のルールも面白い。
ちょこちょこと進めていく予定です。
|
|
2021/03/15〇〇も筆の誤り?
|
|---|
|
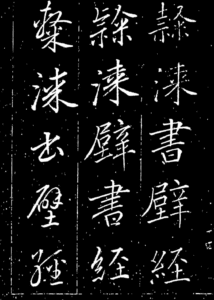 この資料は「三体千字文」という書物の一部です。千字文とはいろは歌の漢字バージョンのようなもので千字を被りなく使つた漢文の長詩で、漢字教育や文字の手本として用いられるものです。 この資料は「三体千字文」という書物の一部です。千字文とはいろは歌の漢字バージョンのようなもので千字を被りなく使つた漢文の長詩で、漢字教育や文字の手本として用いられるものです。
今回の三体千字文は楷書、行書、草書の三体の手本として並べて書かれているものになります。この千字文の書家は、駒字として人気書体のあの先生です。皆さんよくご存じと思います。
さて前振りが長くなりましたが、先日その三体千字文を見ていますと何か違和感があり、よく見てみると3文字目以降、書→壁→経と続くところがなぜか真ん中の行書だけ、壁→書→経となってしまっています。
さあこれは書家の先生が間違えたのか、版を作った人が間違えたのか、気になって仕方がありません。思えば小学生や中学生のころは先生の配ったプリントに間違いを発見しては喜んでいる嫌な子どもでした。大人になってもそんなんではいけませんね。
江戸~明治時代の書物の出版風景に思いを馳せつつ、新しい駒作りに取り組んでおります。
|
|
2021/03/10楽しみなケヤキ
|
|---|
|
先日ケヤキの玉杢の板を入手しました。薄板なので駒箱にしたいと思います。どんな仕上がりになるか楽しみです。

|
|
2021/03/05シャム黄楊で駒木地づくり②
|
|---|
|
前回の続きです。
 輪切りにした材を近くで見てみます。 輪切りにした材を近くで見てみます。
直径は9センチほどで、樹齢は40年ちょっとのようです。
ちょこちょこ黄色いシミが見えますね。
 いきなり様子が変わりまして、丸太を半割して、丸鋸で柾目になるよう板をとりました。この作業はやはり危険なので写真を撮る余裕はありません。 いきなり様子が変わりまして、丸太を半割して、丸鋸で柾目になるよう板をとりました。この作業はやはり危険なので写真を撮る余裕はありません。
 厚みはひとまず10~11mmくらいに挽きました。 厚みはひとまず10~11mmくらいに挽きました。
 一見、沢山とれたように見えますが、この板の場合は真ん中は木の芯があるので使えるのは左右の柾目部分ですが、左には小節、右には黄色いシミが入っています。 一見、沢山とれたように見えますが、この板の場合は真ん中は木の芯があるので使えるのは左右の柾目部分ですが、左には小節、右には黄色いシミが入っています。
なかなか難しいですね。
少し時間をおいて成形したいと思います。
|